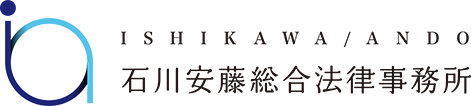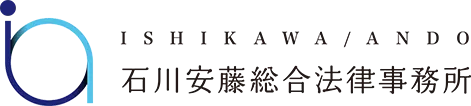遺産の範囲とトラブル解決法
2025/03/29
本コラムでは『遺産の範囲』をめぐる紛争の類型について説明し、その解決手段を説明します。
目次
法律上の遺産とは
多くの方において「遺産」の範囲を考える機会となるのが、遺産分割の手続きでしょう。遺産分割の手続きでは、まず最初に➀遺産の範囲、次に➁不動産等の評価、③特別受益・寄与分の有無等、④具体的分配方法の順で検討し、解決していきます。そこで、遺産分割を進める一番最初に、➀「遺産」の範囲を決めます(全相続人で中間的な合意をするイメージです)。
家庭裁判所の遺産分割調停における説明(法的説明、手続き的説明)を記載すると、遺産分割の対象となる「遺産」とは、「相続時に存在し」かつ「現時点でも存在する」「プラスの財産」です。その上で、全相続人が合意する場合には、その例が認められるというものです(例えば、負債も考慮して分割できます)。
上記の定義にはないですが、「遺産」分割の対象とするかどうか悩ましい問題(争点になるケース)を説明します。
【形見】
形見≠遺産ですので、形見となる動産類については遺産分割の対象となりません。着物、宝石、腕時計が問題になるケースがあります。購入時にはかなり高額なのですが、売却しようと思うと中古品扱いになってしまいますのでかなり値下がり、買取業者ごとに金額がバラバラです。着物、宝石、腕時計等被相続人が身に着けていたような動産類については、相続人の中でも、「遺産」として金銭評価して分割を求める人と、「形見」として遺産分割とは関係なしに特定の人(お孫さん等相続人には限りません)に渡していいのではないか?と意向が分かれるケースがあります。もう1つの特徴が、「特定」「立証」が難しいケースが多いのが特徴です。
「遺産」とするか「形見」(遺産分割の対象外)とするか、全相続人で決めます(大体は、これを分けようと、「遺産」分割の対象を皆で決めるイメージです)。
仮に、相続人間で「遺産」分割の対象とすることが合意できない場合、「遺産」と認めてほしい側が、地方裁判所に「遺産の範囲を求める確認訴訟」を提起する必要があります。
【祭祀財産】
「祭祀財産」とは、御墓(今は霊園から土地利用権を得ている御墓が多いのですが、以前は土地所有権を得て御墓を建てているケースも多く、通常の土地同様に法務局で登記されます。地目は「墳墓」になっています)、遺影、位牌など、先祖のお祀りごとに関する財産です。御墓も購入する時にはかなり高額なのですが、転売できるような財産ではありません。むしろ今後の維持費用の負担が生じます。祭祀承継(財産の承継、費用の負担)は遺産分割とは別の法律問題・手続きですが、全相続人が遺産分割の中で考慮、分割することに合意するのであれば、そのように処理することが可能です。
【受取人が指定された生命保険金】
被保険者が被相続人である生命保険契約は、被相続人が死亡すると(事故発生)、高額な生命保険金が発生します。生命保険金の「受取人」が保険契約で定められている場合、法的に、その生命保険金は受取人の固有財産であって「遺産」ではないと言われています。遺産ではなく、遺産分割の対象外となっています。保険会社が生命保険「契約」に基づいて「受取人」に支払う金銭であるという理由で、被相続人の財産(遺産)ではないと説明されます。ただ、特定の相続人だけが高額な生命保険金を受領する場合、相続人間で不公平感を感じるでしょう。お金の動きを見ても、生命保険契約を締結維持する為、被相続人が相当の保険料を負担しているのですから、保険金を受け取ることができない相続人が不公平感を感じるものと思われます。しかし、遺産ではないだけでなく、特別受益の問題にすらならない(原則論。例外的に考慮する場合あり)とされています。
【生前出金】
被相続人存命中、被相続人名義の預金口座から不自然な出金がされている場合があります。被相続人の生活費として相当額であればいいのですが、過大な、不自然な出金がされている場合があります。特に同居していた相続人が出金していたような場合、被相続人の手元に多額の現金があるor当該出金した相続人が現金を預かっているなどと争いになることがあります。被相続人の判断能力が無い場合には、同居していた相続人が無断で権原なく出金したとして損害賠償請求権や不当利得返還請求権という遺産が存在するという形で争いになることがあります。同居した側が現金をもらったと主張する場合には遺産の範囲の問題ではなく、生前贈与として「特別受益」の議論になることがあります。遺産の問題か、特別受益の問題か、遺産としてどんな遺産なのか?資料に基づき主張を考える必要があります。
なお、被相続人死亡後、特定の相続人が、キャッシュカードを利用するなどして預金の払い戻しをしてしまうケースがあります。「相続時」には存在した預金ですが、「分割時」には存在しないため、原則として遺産分割の対象となる「遺産」ではないとされます。以前は、遺産分割の対象とするためには出金した張本人の相続人を含め残相続人が遺産に持ち戻し、遺産分あkつの対象とすることに承諾しなければ、遺産分割の対象とできないとされていました(家裁の遺産分割の対象とならないため、地裁で別手続きで回収を試みる必要がありました)。しかし、出金した相続人が承諾することは多くの場合期待できませんので、回収のため不合理な負担を強いられていました。今般法改正により、出金した相続人以外の全相続人の承諾で遺産に持ち戻して遺産分割の対象とできると変わりましたので、大きな改善だと思います(但し、当該相続人による出金を裁判所に説明する負担は残ります)。
【負債】
被相続人の負債については、法的には遺産分割の対象ではありません。銀行等貸している側の利益を守るためです。例えば相続人が2人いるとして、長男にプラスの財産を集め、次男に負債を集めたような場合、銀行は相続という偶然により、回収可能性が低くなってしまいますが、それは妥当ではないからです。相続人間において、遺産分割の中で負債も考慮して分割案を協議することはできますが、更に債権者対応が必要です。
相続税申告書上の財産
不動産、預金、株式などの有価証券、農協や信用金庫の出資金、自動車などを遺産分割の対象とするのが一般です。ところで、相続税申告書上、家財一式とか、手元現金を計上することがあるのですが、必ずしも実在特定されていないケースがあります。遺産分割協議では無視することがありますが、相続税申告書と齟齬が生じてしまいますので税理士から遺産分割協議書の内容に記載するように指示されることが多いと思われます。
弁護士の遺産分割交渉と、税理士の相続税申告は、別物(例 不動産の評価は、法律では時価、相続税申告では路線価をベースにした相続税評価額)である一方、協力が必要な場合(例 遺産の範囲、小規模宅地の特例の適用対象の合意)が多いですので、協力関係が重要です。
遺言の効果
遺言があると、遺産分割協議が不要です。遺言書で、特定の相続人に対し或る財産を「相続させる」と記載されます。「相続させる」とは、被相続人が遺産分割の方法を定めたものと説明されており、相続開始と同時に遺産の帰属が決まったことになるため(遺産分割が終わった状態)、遺産分割が不要であり、できないのです。
一方で、長男には3分の2、次男には3分の1のような割合を定める遺言だった場合には、相続割合(枠)が変わっただけですので、誰が何を取得するかの遺産分割が必要となります。
遺産の範囲の確認訴訟
遺産分割手続きの最初の一歩である①遺産の範囲の特定だけでも、考えなければいけないことは多くあります。仮に、遺産分割の対象(「遺産」の範囲の確認)において争いがある場合についてご説明します。
遺産の範囲について争いがある場合の進め方については以下2つかと思われます。
遺産分割全体を「なさず」(遺産分割ができない)と裁判所が判断する場合です。その場合、全体について遺産の範囲の確認訴訟(地裁)をしてから、遺産分割調停(家裁)をやりなおすという進み方です。
ただ、直前出金に基づく使途不明金・現金問題で遺産の範囲が争点になるケースが多いと思われ、その場合には、不動産等遺産であることがはっきりしている財産についてだけ遺産分割を進めるというやり方が多いかと思われます。争いがある使途不明金・現金問題を遺産分割手続きから切り離し、その部分だけ遺産の範囲の確認訴訟などにゆだねさせ、問題ない部分だけについて遺産分割を進めるというやり方です。そのようなやり方が良いかは個別具体的な判断になろうかと思いますので、進め方自体を弁護士と相談することになると思われます。