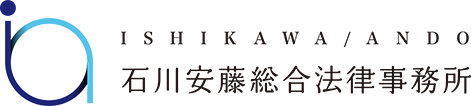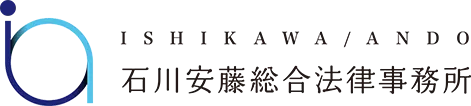不動産時価評価の法的視点
2025/03/27
不動産の評価は、売買、相続、税務など、多くの場面で必要になります。不動産の評価を適切に理解していないと、相手方から不利な条件で遺産分割・遺留分の問題をかたずけられてしまいます。そこで、本コラムでは不動産の評価について説明します。
目次
不動産評価の種類
不動産の評価(ものさし)は、いくつもあると言われます。まずは、代表的な評価を見てみます。
【固定資産税評価額】:読んで字のごとく、毎年、不動産所有者に負担させる固定資産税の金額を計算する元となる評価額です。横浜市をイメージすると、土地については、時価の7割程度と言われています。建物については構造と築年数で変わっていきます。築が古いと大きく減価されます。
【路線価】:税務署で開示します。読んで字のごとく、道路沿いの土地の評価額です。全ての土地にあるわけではありません。路線価図では、路線価の他借地権割合なども記載されています。借地権は財産ですので相続税計算の時の基礎となる財産に含まれます。なお借地権割合は、借地権売買や借地契約でも参考にします。
【相続税評価額】:路線価を元に、相続税評価額を算出します。相続税の金額を計算する元となる評価額です。横浜市内をイメージすると、土地については、時価の8割程度と言われています。なお、建物は固定資産税評価額になります。
【時価】:法律・裁判所の世界では、最終的には、裁判所が任命する不動産鑑定士の鑑定結果(に基づき裁判所が判断した額)をさします。ただ全ての事案で不動産鑑定を行わわけではありません。参考になるのが、公示価格とか、取引価格(不動産業者の査定)とも言えます。ただ、取引価格は需給の影響があり、また土地の利用状況でも変わり、不動産業者の主観も入りますので、業者ごとに幅のある数字になります。
なお、鑑定をするとコストも手間もかかりますので、固定資産税評価額と時価の関係や路線価と時価の関係から、固定資産税評価額÷0.7とか、路線価÷0.8で割戻計算した「みなし時価」という概念で交渉することもあります。
誤解を恐れずに言うと、税理士が着目するのが固定資産税評価額、路線価、相続税評価額、弁護士にが着目するのが時価です。言い方を変えると、税務申告では固定資産税評価額、路線価、相続税評価額が問題となり、法律問題では時価が問題となります。
すると、例えば、相続手続きで税理士に相談する場合と、弁護士に相談する場合で、説明が変わってしまうことがあります。税理士に遺産分割を相談すると、相続税評価額に基づき分割案を説明・提案してしまうことが多いです。弁護士に相談すると、時価に基づき分割案を説明・提案します。事案ごとにどちらが適切かは見解が分かれるとは思いますが、争いがあり、裁判所・法律の視点(遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求訴訟)で考えるべき時は、時価に着目する必要があります。
仮に、相続税評価額を評価(ものさし)として遺産分割案を考えるにしても、税理士が示した金額が、何の特例も使っていないニュートラル確認する必要がありまあります。過去見たことがあるケースでは、小規模宅地の特例(相続税課税の場面で、特定の土地を残しやすいように土地の評価を大きく減価する特例が使えることがあります)適用後の安い評価を混ぜて提案してきたケースがあります。対税務署との関係では土地を安く評価し相続税を安くしてくれるのはいいですが、相続人間の交渉において、このような操作をした数字を提案するのはどうかと思います。えてして、本家である長男側の税理士が関与している事案で、かかる操作された評価が提案してくる危険性があると考えて下さい。土地を取得したい相続人は、土地を安く評価するのが鉄則だからです。
時価(不動産鑑定評価)
不動産鑑定士が計算した結果が不動産鑑定結果ですが、算数・数学の計算のように答えが1つなわけではありません。不動産鑑定の基本となる計算方法が実はたくさん存在します。例えば、取引事例比較法、収益還元法、原価法などがあります。計算方法が異なりますので、結果が異なるのは当然です。これら計算式の1つだけを採用するのはよろしくないとされます。そこで、不動産鑑定書を見ると、これら複数の計算式が記載されており(結果は異なります)、これを検討、調整する作業が行われています。前者は、どの計算式が正しいか鑑定士が意見を述べ、後者は複数の計算結果の平均額・調整額を結論とするものです。
ただ、どれも鑑定士によると言えます。例えば、取引事例法は対象土地近くの似たような土地の相場を参考に金額を出すという方法です。しかし、鑑定士がどのエリアを同一エリア(対象土地の近く)と評価するのか判断が分かれますし、似たような土地を探すべきなのに、恣意的に選んだとしか思えないケースも目にします。
取引事例、収益還元など複数の計算結果をどう調整するのかも鑑定士ごとにかなり異なります。単純に足して2で割るようなものもあれば、特定の計算方法・結果を重視するというようなものもあります(法律が決めていないのです)。そのため、鑑定士の数だけ鑑定結果があると言えます。裁判所が任命する利害関係のない公平な不動産鑑定士は、士業・専門職として公平に仕事をしていると信じていますので、公平な数字が出てくると思われます。しかし、それ以外の私的鑑定(特定の相続人の依頼で行う鑑定)の結果は、十分疑って検討していく必要があります。
不動産鑑定を行うべきケース
法律問題では、時価評価が原則であり、不動産鑑定士による時価評価で検討するのが公平と思います(先ほど不動産鑑定が必ずしも信用できないとしましたが、裁判所鑑定は利害関係のない専門職によってなされますし、裁判官が尊重しますので重要な物差しです)。そこで、手間とコストを気にしなくていいのであれば、全て裁判所手続きをとったうえで、不動産鑑定を実施してもらえばいいということになります。しかし、相続人=家族・親族ですので、何でもかんでも裁判所手続きをとるのがいいか?というとそんなことはありません。また、裁判所に遺産分割調停申立てを申し立てても、裁判所が自主的に、不動産鑑定を実施してくれるわけではありません。相続人において鑑定の申立てを行い、費用を収める必要があります。しかも鑑定費用が結構高いのです。通常の戸建て不動産クラスでも平気で50万円~はします。そのため、不動産を複数所有している場合は鑑定費用だけでも何百万円!?となってしまいます。そこで、双方の主張額にあまり開きが無いとか、コストが無い場合には、あえて鑑定をしないという選択をする必要があります。ただ、単に官邸から逃げるのではなく代替案で進める合意をとるところ(例 みなし時価を用いるとか、不動産業者の査定額を調整するとか、評価額の争いの小さい不動産はみなし時価や不動産業者の査定額で評価合意し、争いがある不動産に限って鑑定を選択するなどです)が弁護士の腕の見せ所であり、勘所かと思います。