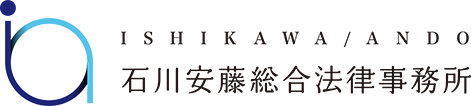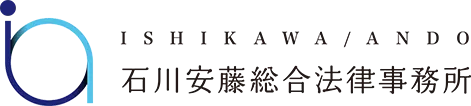弁護士におけるサイン証明の実際
2025/03/27
近年、サイン証明を要するケースが増えてきています。サイン証明は、読んで字のごとく、書類や契約書になされたサイン(署名)が署名した本人のものであることを証明する制度・証明(書)です。本ブログでは、サイン証明を必要とするケースの典型例として遺産分割協議書を説明します。
目次
遺産分割協議(一般論)
遺産分割の解決手段は、一般的に、①裁判所外の話合い手続きである遺産分割協議(当事務所では、遺産分割示談交渉と呼んでいます)、②裁判所での話合い手続きである遺産分割調停、③遺産分割調停が不成立だった場合に裁判所が判断する遺産分割審判(裁判手続きの1つです)があります。このうち、遺産分割協議をまとめるときにサイン証明を要する場合があります。
遺産分割協議による話合いをまとめるとき、一般的には、遺産分割協議「書」を作成します。そして、遺産分割協議「書」には、全相続人が署名し、実印を押して、印鑑登録証明書(原本)を添付します。
遺産分割協議は、全相続人が合意することが必須です。相続人の1人でも反対している場合には、他の全相続人が合意していても遺産分割協議は成立していません。何も解決していないといっても過言ではありません(なお、話合い解決ができる特定の相続人との間だけで先行して紛争を解決を図る際に「相続分譲渡」という制度を利用することがありますが、これは別のコラムで記載したいと思います)。
ところで、一般的には、遺産分割協議「書」を作成しますが、実は口頭合意だけでも遺産分割が有効に成立する場合があります。遺産分割協議は、書面が必須とされる要式行為ではないのです。そもそも法律行為の全てが書面を要するわけではないのです。例えば、売買契約も要式行為ではありません。不動産の売買契約では「通常」売買契約書を作成しますが、八百屋でキャベツをを買うとき「売買契約書」は作成しないでしょう。前者は対象が高額であるとか、約束事が多いとか、証拠を取っておく必要が多いとかの事情によります。しかし、仮に不動産を口頭合意だけで売買していいか?と質問されれば、答えはYesなのです(無論、トラブル回避のためにも、勧められる方法ではありません)。
遺産分割も口頭合意で構いません。そのため、仲のいい相続事件、特に遺産が預貯金しかないときに、遺産分割協議「書」を作らないで、払い戻した金員を相続人間で分配するだけ(分配を口約束)といったケースは多いのではないでしょうか。
それなのに、遺産分割協議「書」を作成するのは、大事な約束事だから証拠に残すという意味と、金融機関が預貯金の解約払い戻しをする際や、法務局が相続に基づく所有権移転登記手続きを進める際に、遺産分割協議「書」を要求してくるからです(遺産分割のために書類が必要なのではなく、預貯金払い戻しや登記手続きのため書類が必要なのです)。そして、金融機関や法務局は、遺産分割協議「書」には、「実印」で押印すること、「印鑑登録証明書」を添付すること、各書類は原本であることを求めます。そこで、一般的には、遺産分割協議「書」に、全相続人が署名、「実印」で押印し、「印鑑登録証明書」を添付するのです。完ぺきな遺産分割協議書ですね。
印鑑登録証明書の添付が無い遺産分割協議書は?
遺産分割協議「書」はあるが原本が無い場合とか、遺産分割協議「書」はあるが印鑑登録証明書が無い場合等、先に説明したような完ぺきな遺産分割協議「書」が無い場合があります。時々、このような状態であることを理由に、遺産分割の合意を相手方相続人が覆そうとしてくる場合についての相談があります。また、印鑑証明がないから遺産分割協議は成立していないとの前提で相談に来られる方がいます。しかし、先の説明でお分かりになると思われますが、口頭でも遺産分割協議は成立するくらいですから、遺産分割協議「書」の原本がなくとも(コピーしかなくとも)、印鑑登録証明書がついてなくとも、遺産分割協議は成立済みです。そのため、「まだ遺産分割協議が成立していない」と不合理な主張をしてくる相続人に対抗することは十分可能です。無論、金融機関での預貯金解約払い戻しとか、法務局での所有権移転登記手続きには、完ぺきな遺産分割協議「書」が必要になりますので(原本が必要、実印で作成が必要、印鑑登録証明書が必要)、それら手続きを進めるため、裁判所手続きを要しますが、遺産分割での合意自体を覆されるわけではありません。無論、完ぺきな遺産分割協議書が無いケースは好ましくありません。最終的確定的合意がなされていないから印鑑登録証明書が交付されなかったなど事情もあるケースもありましょうから、完ぺきな遺産分割協議書を作成するようにするべきです。証拠レベルの視点でも、実印は重要書類作成時に求められますので、わざわざ実印を押すというのは、内容を理解・納得し署名押印したことをうかがわせる事情ですので、勘違いなどの主張にも争いやすくなります。しかし、完ぺきな遺産分割協議書が無くてもあきらめる必要はないですし、相手方の不合理な対応には戦うべきと考えます。
サイン証明の役割
日本人であれば、住民票を置く必要・義務があります。住民票を置いた役場で印鑑登録をすることができます。実印とは、特別な印鑑ではなく、役所で印鑑登録した印鑑に過ぎません。大きさなど形式的要件はありますが、文房具屋で購入した数百円の印鑑でも登録可能です(登録により実印になります)。以前と異なり、外国人の方も、要件さえ満たせば住民票を置くことができ、印鑑登録をすることが可能です。一方で、日本人(日本国籍の方)でも外国に長期居住している場合には、住民票を抜くことになり、その場合、印鑑登録も廃止されます(日本に帰国した際に、再度住民登録をして印鑑登録をすることは可能です)。最近、海外に移住・長期滞在する日本人が増えたため、相続事件で、相続人の一部が外国にいるケースをかなり多く見るようになりました。遺産分割について交渉し、合意できることになったので遺産分割協議書を作成しようとすると、実印・印鑑登録証明書が必要になるのです。しかし、日本に住民票が無いと、印鑑登録ができませんので印鑑登録証明書は用意できません。また登録が無いですので実印もありません。そこで必要になるのがサイン証明です。遺産分割協議書のサイン(署名)が、本人によりなされたものであることを証明することで、実印+印鑑登録証明書に替えて、完ぺきな遺産分割協議書とするのです。
サイン証明と遺産分割協議書
外国在住の相続人(日本人)については、日本領事館にて「在留証明書」と「署名(および拇印)証明書」
を入手します。具体的には、遺産分割協議書をメール等にて送って印刷してもらい、日本領事館に同協議書を持参、領事館にて署名と拇印を押捺して、同協議書に「署名(および拇印)証明書(貼付型)」を合綴してもらいます。遺産分割協議書にされた署名が本人のものであると証明してもらいます。
または、同様に領事館にて「在留証明書」と「署名(および拇印)証明書(単独型)」を入手します。遺産分割協議書とは無関係に、署名が本人のものであることを証明してもらいます。そして、「在留証明書」(及び「署名(および拇印)証明書」)を取得した上で、日本の公証役場に遺産分割協議書を持参し、公証役場にて公証人の面前で協議書に署名し、「私署証書認証」を合綴してもらいます。
※日本国籍を離脱した元日本人は、領事館対応ができないので、現地公証人にお願いします。
※「署名(及び拇印)証明」は、印鑑登録証明書の代わりといえます。なお、在留証明書は、住所確認のための書類として必要になります。
※なお、上記は、印鑑登録証明(書)が無い相続人について、印鑑登録証明書に代わる手続き・書類になります。その他の日本にいる相続人は、遺産分割協議書に実印(印鑑登録をしていない場合はまずは印鑑登録)で押印し、印鑑登録証明書を添付します(普通の遺産分割協議書作成時と同じです)。