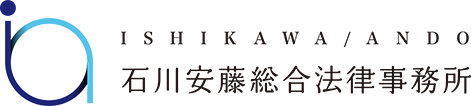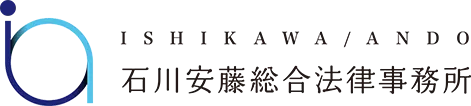特別受益における相続の真実
2025/03/21
相続事件で「特別受益」が問題になるのは、①遺産分割事件と、②遺留分侵害額請求事件の2つのケースがあります。同じ相続事件でも、この2つの場合で微妙に扱いが異なりますので、本コラムではこれについて説明します。
目次
特別受益とは?
特別受益とは、典型例が、被相続人から特定の相続人に対する生前贈与です。但し、全ての生前贈与ではなく、民法において「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」と規定されています。そのほかにも、特定の相続人が被相続人から特別扱いを受けた場合(土地を無償で貸してもらっているような場合)なども考えられます。本コラムでは、生前贈与にフォーカスしてご説明します。
❶遺産分割事件は、家庭裁判所の調停手続きで特別受益についても考慮した交渉を行い(調停申立ての前に、裁判所外で話合いをするか否かは任意です)、解決しない場合には、遺産分割事件が「審判」手続き(裁判所の裁判手続き)に自動移行し、特別受益の問題も「審判」で判断されます。
これに対し、②遺留分侵害額事件は、家庭裁判所の調停手続きで特別受益についても考慮した話合い行い、解決しない場合には、調停手続きは「不成立(不調)」となります。この場合、請求する側が、地方裁判所に、遺留分侵害額請求事件について改めて「訴訟」提起する必要があります。自動的に裁判所の裁判手続きになるわけではありませんし、裁判所も異なります。
特別受益の特殊性
法的手続きでは、「主張」と「立証」という概念があります。「主張」とは「言い分」です。請求する側の「言い分」を相手方が認めれば「立証」は基本的に不要です。請求する側の「言い分」を相手方が否定した場合、請求する側は、自分の言い分を基礎づける証拠を提出する必要があります(立証という考え方です)。
話合い手続きでは(裁判所外の示談交渉でも、裁判所の調停でも)、双方が納得・合意すればよいので、厳密な主張・立証を要しないケースも多いですが、遺産分割「審判」や遺留分侵害額請求「訴訟」といった裁判所の裁判手続きでは、主張(言い分)レベルからかなり厳格なことを言われます。また、証拠として不十分ですと、裁判では認めてもらえません。
相続事件における特別受益は、当事者の片方がいないこと(贈与した側の被相続人は死亡しています)、贈与を家族間の問題であること(贈与契約書を作るケースは少ないと思われます)、長期にわたったり、古い問題であるケースが多いことが、特徴といえます。
被相続人は、ご高齢で亡くなりますので、例えば、「昔」、長女の結婚式費用を援助したとか、次男の自宅の購入費用を援助したとか、長男だけ大学進学費用を出してもらった(自分は、高校までしか行かせてもらえなかった)などと主張されることがあります。よくありそうな話ですが、考えなければいけないことは多く、どう攻めるか?、どう守るか?弁護士の腕の見せ所です。
主張(言い分レベル):「自宅購入費用の援助」のような生前贈与は、特別受益の「主張」として通常は問題となりません。ただ、被相続人である「父」から贈与されたのか、「母」から相続されたのか?場合によっては両親2人から贈与されたのかが問題になるケースがママあります。また、相続人本人ではなくその配偶者に対する贈与の場合もあります(特別受益は「被相続人」からの「相続人」に対する生前贈与ですので、渡した側、受け取った側いずれもに問題点があることがあります)。
また、税務署対策で、「贈与」ではなく「貸金」になっており、金銭消費貸借契約書は作られているものの実際には返済がされてない場合、「貸金」だから「贈与」ではないといっていいのでしょうか?
主張(言い分)レベルで難しい問題が生じることがあります。
立証レベル:現在、金融機関は、取引明細を10年分しか保存していないとか、開示できないと説明するところがほとんどです。すると、被相続人であある父が、「20年くらい前に」、自宅購入「費用」を援助したと説明していたような場合、証拠上の問題が生じることが非常に多いです。
通帳に記帳が残っていないような「現金授受」や、通帳が残っていないとか金融機関にて取引明細が出せないという10年より前ですと、「贈与時期」や「贈与額」が特定しがたく、そもそも主張面で問題が生じるのですが、それ以上に立証面で難が生じるのです。証言や、間接的な証拠も証拠ですが、やはり、通帳や銀行取引履歴にきっちり印字されている場合とは状況が異なってしまいます。
遺産分割と特別受益
遺産分割事件では、古い特別受益でも理屈上は問題がありません。20年前の特別受益も考慮されます。
※ただし、前記の通り、主張・証拠上の問題点はありますので、弁護士の腕の見せ所かもしれません。
※一方で、被相続人が、遺産分割の際、特別受益を考慮しないでほしいという意思表示をしている場合(持ち戻し免除の意思表示)、考慮しません。
※なお、本コラムでは割愛しますが、寄与分も考慮します。
異臭分侵害額請求と特別受益
最初に、遺留分(侵害)額の計算の基礎となる金額を計算することから始まります。相続開始時に残っていた遺産に対象となる特別受益を持ち戻して計算し(遺産額+特別受益額。また相続債務など控除するものを計算します)、遺留分割合をかけて、遺留分額を計算するという計算式で考えます。いわば、これが主張(言い分)です。
この点、遺産分割事件と異なり、遺留分侵害額請求事件では、「特別受益」の扱いが若干異なります。遺留分侵害額請求については、民法条文が以下のようになっています。
第千四十四条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
令和の相続法改正で設けられたのですが、3項に「十年」という制限が設けられました。そこで、持ち戻しの対象となる生前贈与は相続開始前10年分に限られることになります。
例 遺産がほぼなく、長男が生前贈与で3000万円を受領していた場合で考えてみます
生前贈与が3年前の場合、3000万円の生前贈与を考慮して(持ち戻して)遺留分を計算し、長男に遺留分侵害額請求を行うことが可能です。無論、主張・立証の問題はありますが、3年前ですので銀行取引履歴も残っており、主張・立証しやすいケースも多いと思われます。
一方、生前贈与が13年前の場合、そもそも3000万円の生前贈与を考慮して(持ち戻して)遺留分を計算することが認められないのです。
※請求される側にとっては、生前贈与を受けたのが10年前か否かで大きく変わります。一方で、1項が「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは」持ち戻しすことを認めていますので、10年以上前の生前贈与でも考慮される場合があると考えられます。
※被相続人が、遺留分額計算の際、特別受益を考慮しないでほしいという意思表示をしていたとしても、遺留分を侵害するような意思表示は認められません(持ち戻し免除の意思表示に、遺留分が優先します)。遺留分は遺留分権者への最低限の保証という制度だからです。遺産分割とは異なります。
※なお、本コラムでは割愛しますが、寄与分は考慮しません。遺産分割とは異なります。
専門家の助力が重要な分野
特別受益や寄与分は、法定相続割合を修正し相続人間の公平を図る制度であり、特別受益は遺留分の計算で重要になります。しかし、主張(言い分)レベル、立証レベルで難しい場合が多く、まずは専門家に相談し、助力してもらった方がいい分野といえます。