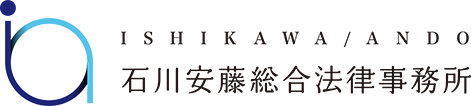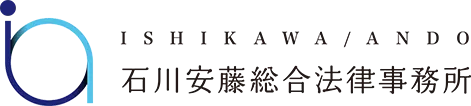遺産分割協議書作成に必要な書類とは
2025/03/19
遺産分割の手続きは、①裁判所外の話合い(遺産分割協議とも遺産分割示談交渉とも。本コラムでは「遺産分割協議」と呼びます)、②裁判所を使った話合い(遺産分割調停)、③裁判所の裁判(遺産分割審判)で約束事を書面化します。
遺産分割調停の場合、裁判所で、必要な情報を記載した「遺産分割調停調書」を作成してくれます。
遺産分割審判の場合、裁判所が、必要な情報をまとめた「遺産分割審判書」を作成してくれます。確定が必要ですので確定後「確定証明書」を出してくれます。
法務局で不動産の相続登記(被相続人→承継者への所有権移転登記)の申請をする場合や、金融機関で預金の解約払い戻しをする場合、「遺産分割調停調書」や「遺産分割審判書」(及び確定証明書)を必要書類を添付します。相続人全員が実印・印鑑証明で作成した「遺産分割協議書」は不要です。戸籍も不要です。
※登記申請書とか、金融機関の相続手続き依頼書といった申請書類の作成は必要です。但し、全員の署名・押印などは不要です。誤解を恐れずに言うと、「調停調書」「審判書」があれば、一人で粛々と手続きが進められます。
※もっとも、内容に問題があると、手続きが止まります。裁判所でも注意して作成してくれますが、法務局や金融機関のルールは知りませんので、問題がある(手続きがとん挫してしまうケースもママあります)。弁護士への相談、依頼を強く勧めます。弁護士が関与する場合、裁判所の指示もあり、金融機関に事前に調停調書を確認してもらうなどのケースも多いです。
※逆に、金融機関は、裁判所手続き・相続手続きを必ずしも理解していません。そのため、誤解した質問や必要書類の指示をしているケースがあります。疑問に思ったら弁護士にご相談ください。
「遺産分割調停調書」や「遺産分割審判書」で、登記・預金解約手続きを取る場合、書類がシンプルなのがご理解いただけたと思います。
一方、裁判所を利用すると、手続きも重いですし、時間もかかるケースがあります。全ての遺産分割事件が家庭裁判所を利用しているわけではありません。本コラムでは、裁判所を依頼しない「遺産分割協議」「遺産分割協議書」について説明します。
目次
遺産分割協議書とは
多くの方は、相続があり遺産を分けるときには「遺産分割協議」をして、合意する場合には「遺産分割協議書」を作成し、署名・「実印」で押印し、「印鑑証明書」を添付するものだと、漠然と考えられていると思います。概ね正しいです。最初に、「遺産分割協議書」ではないものをご説明します。
その典型例が、金融機関の「相続手続依頼書」です。例えば、相続人が兄弟2人のケースで、相続人の一人が、金融機関の窓口に行き払い戻しを依頼すると、「相続手続き依頼書」の作成を求められます。一般的には、銀行で用意したひな形に、①代表者1人が最初に署名・実印で押印すること、②代表者以外の相続人全員も署名・実印で押印すること、③戸籍一式や相続人全員の印鑑証明書の用意を求められます。遺産の内容(支店・預金の種類や口座番号を記載する欄がありますが、金融機関で指示してくれます)。➃解約した預金を誰の口座(代表相続人名義の口座であることが多いと思われます)に送金するかも記載します。この書類を提出して手続きを進めると、指定の口座に解約金が振り込まれます。代表者は、相続人全員との(クチ)約束に従い、お金を帰属させます。仲の良い相続人であればそれでいいです。しかし、「相続手続依頼書」は、金融機関対全相続人の書類に過ぎず、相続人対相続人の書類ではありません。要は、相続人は、代表相続人に解約・受領を任せたとの「対金融機関」用の手続き書類に過ぎないのです(解約により受領した金員の分配は相続人らで別途解決して、金融機関には迷惑をかけないとの書類に過ぎないのです)。そのため、相続人間では約束が成立していることを証する書類ではありません。遺産として預金のほかに不動産がある場合、通常、預金を2分の1宛、不動産も2分の1宛(共有)とはしませんね。私は預金をもらう、私は不動産をもらう(差額は調整金)とするのではないでしょうか?このように、相続人間で遺産をどう分けるのかが「遺産分割協議書」であって、金融機関の「相続手続き依頼書」は、解約のための手続き依頼書に過ぎないのです(無論、遺産分割協議書を作成したうえで相続手続き依頼をする場合もあります。遺産分割協議書があっても、対金融機関との問題で、解約の手続き書類を作成する必要があり、それが相続手続き依頼書なのです)。
相談者様の中には、「何かの書類」に署名・実印で押印し、印鑑登録証明書を交付したとの認識があるものの、それが「相続手続き依頼書」に過ぎないのか「遺産分割協議書」なのかわかっていない方が非常に多いです。
いうまでもないことですが、印鑑を押すとき(特に実印)は、内容をよく確認してくだい。また納得できな場合は印鑑を押してはいけません。書類に書いていないクチ約束は、法律の世界では存在しないものと考えてください。
遺産分割協議書の体裁(一般)
遺産分割協書の作成:一般的には、署名・実印で押印します。実印単体では意味がないので、印鑑登録証明書を添付します。
遺産分割協議書の部数:一般的には、相続人の人数分作ります。
遺産分割協議書を使う場合:相続戸籍一式(相続人を特定するのに必要な全戸籍、相続人の現在戸籍)が必要です。また法務局に登記手続き申請をする場合には登記申請書(その他登記手続きに必要な書類)や、金融機関の相続手続依頼書といった手続き書類が必要になります。
こんな場合には?
前記で記載したような完璧な遺産分割協議書と必要書類がそろっていればいいのですが、意外と、完ぺきにそろっていない場合があります。
例えば、実印で押印していないと、実印で押印しているようだが印影がはっきりしない場合
例えば、(実印で押印しているが)印鑑証明書が付いていないとか、印鑑証明書がコピーの場合
また、遺産分割協議書のコピーしかない場合
体裁・必要書類がそろっていない場合、遺産分割協議は成立していないのでしょうか?
しかし、遺産分割協議書に「実印」が押してなくとも、「印鑑証明書」が添付がなくとも、遺産分割協議書のコピーしかなくとも、遺産分割協議自体は成立していることがあります。極論すると、「口頭の遺産分割協議」でも有効なのです。ただ、証拠の観点から争われたり、実印ではない、印鑑証明がない、コピーの場合、法務局や銀行が受け付けてくれないだけなのです。そこで、これら体裁面の問題点を理由に遺産分割手続きを覆そうとする相手方に対しては、(家庭裁判所の遺産分割調停ではなく)地方裁判所の訴訟手続きの方が適している場合もあります。
なお、注意点は、「(確定)合意」か、「交渉段階」かの区別です。
例えば、「不動産は長男」、「預貯金は長男、長女、次男でわける」というところまで話がまとまっていたとしても、預貯金の分配額その他条件が定まっていない場合には、「確定合意」問いは言えない(交渉段階)の場合が多いといえます。わかりやすい例でいうと、AがBに不動産を3000万円で売ってよと申込み、BがAに対して、いいよといった場合を考えてみてください。確かに、不動産を3000万円で売買するという話し合いはできました。しかし、手付金をどうするのか?決済時期をどうするのか?境界画定などの条件は?といったように、確定合意ではなく、単に交渉段階に過ぎないのです。
遺産分割協議書作成には弁護士の関与が好ましい
家庭裁判所の調停調書・審判が完璧だとは言いませんが、問題があるケースの方が圧倒的に少ないでしょう。一方、私人が作る遺産分割協議書の場合、結構問題があるケースが多いと思われます。円満な相続人間であれば、遺産分割協議書に必要事項の記載が抜け落ちていたとしても(極端な場合、相続人の勘違いがあったとしても)、再度交渉し作り直せばいいでしょう。しかし、対立が激しい相続人間の場合、間違いがあっても再度遺産分割協議書を作りなおしたり、印鑑証明をもらうことが難しいケースが多いと思われます。裁判所を使わないということは、それだけ自己責任の側面が強くなります。できるだけ、弁護士が関与するのが好ましいと考えます。
なお、相続税申告が必要な規模の遺産分割では、(相続税の相談・依頼を受けている)税理士が遺産分割協議を主導し、遺産分割協議書案を提案するケースがあります。無論、合理的な場合もありますが、2つの大きな問題があります。❶法律上、遺産分割は時価で考えます(不動産は時価で評価します)。しかし、税理士は、相続税評価額で計算することが多いです。各相続人が相続税評価額と分かって納得するのであればいいですが、特例を使って低い評価額が混じっていおる可能性もあります。きちんと説明を理解する必要があります。❷税理士は基本的に依頼者の弁護はしてくれないということです。弁護士は、各相続人から依頼を受け相手方と戦います。全相続人の間を調整する業務は基本的に行いません。遺産分割は、潜在的に利害相反を有する事件なのです。遺産のパイは決まっていますので、長男が多く取得すれば、次男の取得額が少なくなるという利害相反が常に存在するのです。そこで、弁護士法上、利害相反がある受任は厳しく制限されているのです。一方、税理士は、特定の相続人から依頼を受け、他の相続人と戦う(交渉する)職種ではないのです。あえて言うのであれば、税理士は、対税務署と戦うのです(相続税の節税)。そこで、相続人間で戦わなければならない遺産分割事件は、弁護士に依頼するべきなのです。