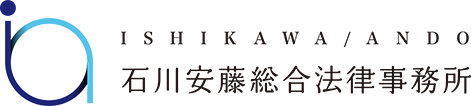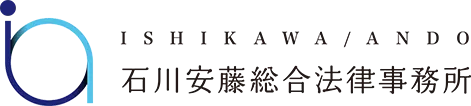特別寄与料改正法案の実務解説
2025/03/18
平成30年の法改正にて、新たに「特別寄与料」という制度が設けられました(令和元年7月1日以降請求可能)。本コラムでは、特別寄与料についてご説明します。
目次
寄与分
以前は、「寄与分」という概念・制度だけが存在しました。言葉だけ見ると「寄与分」と「特別寄与料」は「寄与」という点で似ている感じを受けるかもしれません。違いを正しく理解する必要があります。
現在の相続事件(遺産分割事件)では、戦前の長子優遇はなくなり、「法定相続割合」による公平な分配が大原則です。遺産分割は、①遺産の範囲の特定、②不動産等の評価、③特別受益・寄与分による法定相続の修正、➃具体的分配です。「寄与分」は、法定相続を修正することが公平な相続になるだろうという場合に採用すべき、(法定相続の原則に対し)特別、例外的な概念・制度です。
例えば、重い認知症の母親(父は他界。相続人は長男と・次男のみ)と同居し介護に尽力した次男がいる場合、次男と、介護等何もしなかった長男が同じ2分の1の割合での遺産取得とすることが公平化?と考えたとき、法定相続割合での相続がかえって相続人間では不公平ではないかと考え、特別な寄与があった次男の遺産取得を増やして公平な相続を実現しようとするものです。
他にも、同居する長男が、ほぼ無償で父親の家業を手伝っていた場合、父親の遺産の一部に長男の貢献が混じっているような場合、父親の遺産を2分の1の割合で承継させると、かえって不公平ともいえるでしょう。
そこで、特定の場合に「寄与分」を認め、法定相続割合を修正した相続とするのです。
寄与分が認められる場合
私見ではありますが、同居する相続人と、同居しない相続人の間に何らかの負担(感)に差があるのは致し方ないといえます。例えば、元気なご両親でも、同居する相続人が「気を遣わなければならない」とか、「年に数回、病院に送迎した」場合、同居せず気兼ねなく生活する相続人、何も手伝わない相続人とでは、負担(感)が異なるでしょう。
しかし、このような負担(感)全てが、寄与分として考慮されるわけではありません。通常の親族関係を考慮しても、特別な寄与があったといえる特別な場合に限って、「寄与分」が認められます。以前、裁判官が比ゆ的に「皆さんは、赤ちゃんの頃、ご両人に無償で面倒を見てもらいました。ご両親は年を取って赤ちゃんに戻ったのと同じです。それを考えたら何でも『寄与分』としてお金・経済的に換算することは相当ではありません」と
」説明していました。
そこで、ちょっとした介護の事実があっても「寄与分」は認められません。しかし、徘徊している場合とか、おむつ交換などシモの世話をしていた場合など、特別な介護と考えた方がいい場合に「寄与分」が認められます。
特別寄与料の制度が設けられた趣旨
「寄与分」は、相続人が特別の寄与をした場合に認められた制度です。以前の法律は、これで公平が実現できると考えていたのです。しかし、実際には、これでは公平が実現できない、介護した人の苦労が報われないケースが多数存在したのです。
例えば、先の例で、同居し介護をしたのが相続人である次男であれば、次男の「寄与分」を認定し、公平な相続の実現も考えられました(無論、完全に公平化は別問題です)。しかし、実際には、次男は会社員で、次男の配偶者が義母の介護をするといったケースがよく存在します。しかし、介護をしたのが相続人ではない次男の配偶者ですと「寄与分」が認められません。繰り返しになりますが、「寄与分」は、相続人だからこそ認められるのです(相続人であることが前提です)。すると、次男の相続分が増えることはなく、相続人の配偶者の労は何も報われないのです。
そこで、「特別寄与料」という新しい制度を作り、相続人ではない方の特別の寄与に報いることにしたのです。具体的には、相続人ではない方にも、遺産の一部を取得させることとしたのです。「寄与分」と異なり「特別寄与料」は相続人ではない方のための制度です。
特別寄与料
「特別寄与料」は、被相続人の相続手続きにおいて、相続人以外の人が、被相続人のために特別に貢献した場合に遺産から払われる金銭的な報酬といえます。相続人以外の親族等が、被相続人に対して生活の援助や特別の支援を行った場合、その貢献に対して金銭的支払いを実現する制度です。例えば、長期間にわたり被相続人の面倒を見てきた場合等が考えられます。「寄与分」が相続人に認められる制度、「特別寄与料」が相続人ではない人に認められる制度ですが、特別な貢献があった場合に認められるという点では共通です。どのような場合に認められるか、認められるとしてどの程度の経済的評価がされるべきかは難しい問題ですので、専門家への相談をお勧めします。
その他(特別縁故者)
更に、以前からある別な制度に、「特別縁故者」という制度があります。これは、相続人ではない人が、被相続人と特別な関係があった場合(先ほどの長期間生活の面倒を見てきたような場合です)、遺産の全部または一部を取得できる制度があります。但し、これは、「相続人がいない場合」に認められる制度であり、相続人がいる場合に認められる「特別寄与料」とは根本的に異なります。
注意点
このように「特別寄与料」は、以前の不公平な結論の修正を目指し新たに設けられた制度として積極的に評価されるべきと考えます。しかし、この制度が使いにくいのは、特別寄与者は、相続の開氏及び相続人を知ってから6カ月以内、または相続開始後1年を経過してしまうと、請求できなくなるという、かなり厳しい期間制限があることです。そこで、疑問がある方は、早めに専門家の相談を受けるべきです。